
共に生きることが
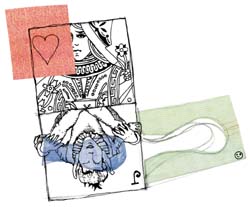 かつて私が子どもだったころ。皆がいる場で、お菓子などを一人で食べようものなら「分けてから食べるのよ」。叱(しか)られたものだ。親、きょうだいがそこにいることの意味を躾(しつけ)られた。「いっしょに生きていること」が日常の中で教えられていたのだ。そんな在り方は、どの家にも自然にあった。
かつて私が子どもだったころ。皆がいる場で、お菓子などを一人で食べようものなら「分けてから食べるのよ」。叱(しか)られたものだ。親、きょうだいがそこにいることの意味を躾(しつけ)られた。「いっしょに生きていること」が日常の中で教えられていたのだ。そんな在り方は、どの家にも自然にあった。今の子どもを見ていると、傍らに誰かがいても、「分ける」とか「食べますか?」などという行動を取らない。その状況を見るにつけ、私はある恐れを感じる。「人間関係」の希薄さだ。そこに自分以外の人間がいる、という意識が働かないのだ。彼らが大人になった時、社会生活をスムーズに送ることが、一体できるのだろうか。
こんな話を聞いた。小学校の給食での出来事。分けられたカレーに、自分の肉の量が少ないと感じたある子どもが、親に訴えた。親は学校に、不公平を直すよう要望した。「平等」でないからという理由からだった。私はその話を聞いて、「平等」の意味が間違った方向へ向かっている思いを深くした。肉の量が少ないのを子どもが不満に思う。それは別に悪いことではない。その不満を親に言ったとしても、それはそれで良い。しかし親が学校へ抗議をするというのはどうだろうか。「少しぐらい違いがあってもふつうのことよ。人が分けるのだもの」。その程度の説明で子どもは納得するのではないか。
他にこんな話も聞いた。私のかつての教え子が勤めている幼稚園での出来事。ある母親が子どもを幼稚園に送って来た。子どもは母親と離れるのを嫌がって激しく泣き出した。するとその母親は、隣にいた園児の持っているおもちゃを取り上げ、「はい」と自分の子どもに渡した。子どもは泣きやみ、にこにこしていた。
ふたつの話に、私は共通したものを感じる。それぞれの母親が取った行動にはどこか「人の気配」が感じられない、ということ。要するに「他人が見えない」のだ。「共に生きている」そんな感覚が備わっていれば、ふたつの話は生まれなかっただろう。カレーライスの親は「平等」を主張したいのだろうが、他人との関係で成り立っている世界を見ていない。幼稚園の話は、その究極だろう。「平等」とか「権利」が他人との関係の中で根付いていないことに、私は恐れを感じるのだ。これらのケースのみならず、そのような心の動きはどの家庭にも忍び寄っているのではないか。表れ方はさまざまであっても。「分けあう」ことより「してもらう」ことに心が傾いている。
家族の中で何げなく教えられてきた「他人と共に生きている」という感覚。それは今では、遠く、背後に押しやられているような気がする。
2003年4月13日掲載 <58> |
| メニューへ戻る |
|---|